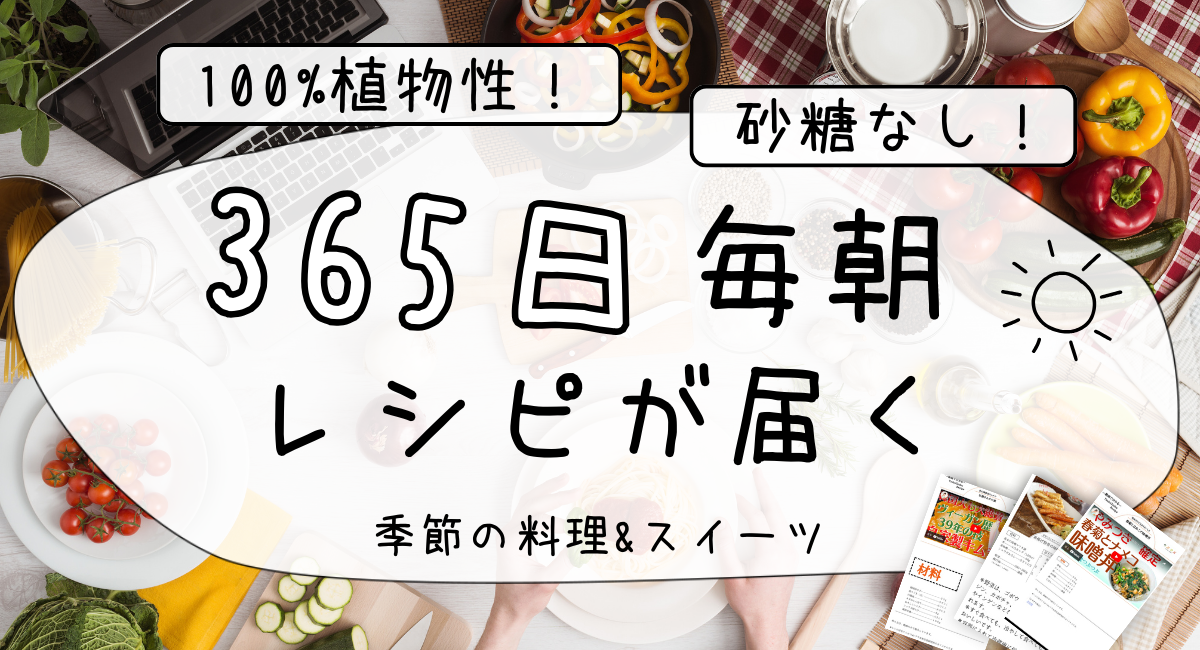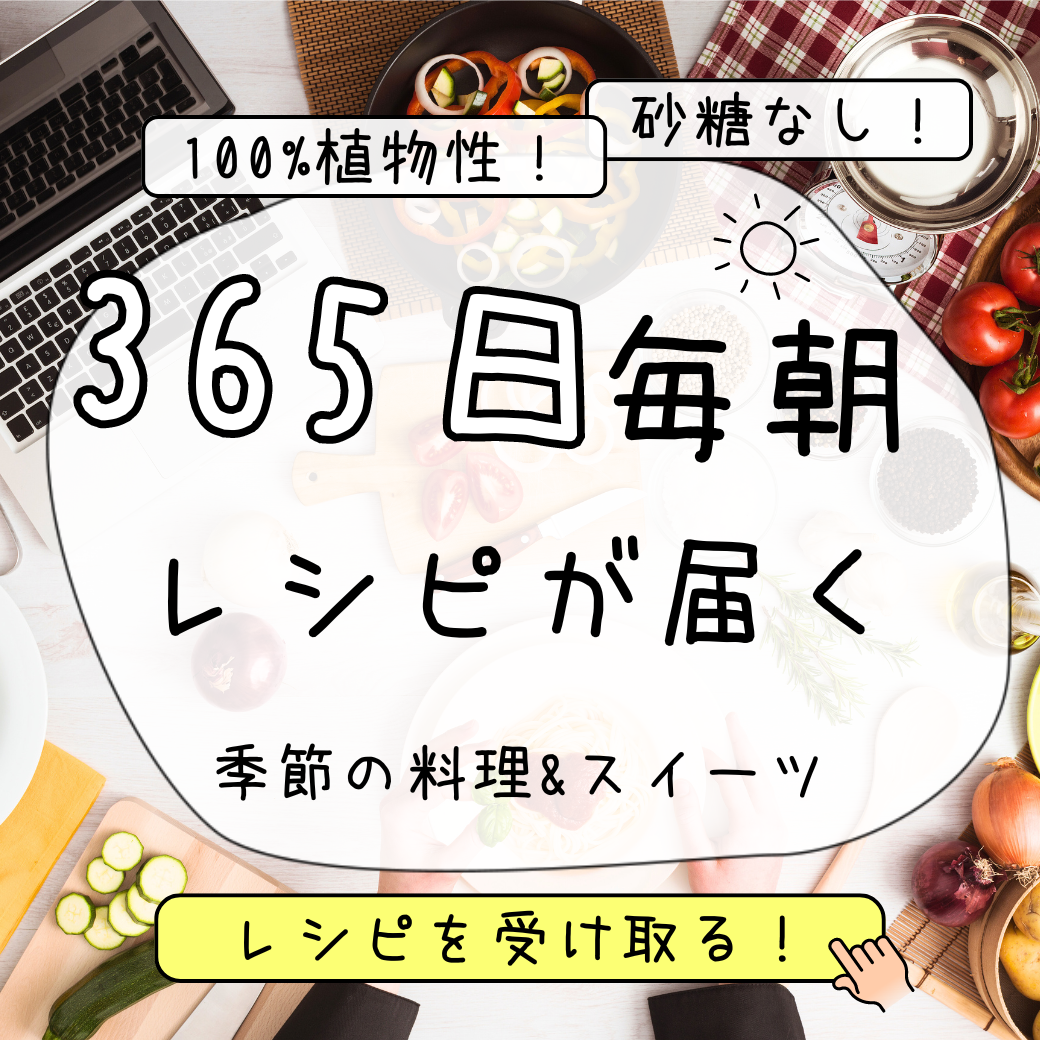【油の話 vol.4】いのちの巡りから生まれる菜種油 前編

*この投稿は以前発刊していた会報誌『月刊つぶつぶ』より特集シリーズ「特集 油 〜健康を支える油、健康を損なう油〜」から一部編集して掲載しています。連載一覧はこちら
前回記事では、菜種油が必須脂肪酸含有量が多く栄養バランスに優れた植物油であり、その内容や効能についてご紹介しました。今回は菜の花、菜種油と私たちとの関わりや歴史について解説します。
菜の花畑は心と体を癒す春の栄養
春、南から北上する一面に広がる菜の花畑は、日本の風景の原点でした。緑を覆うように広がる鮮やかな黄色の絨毯は目にも心にも強烈に焼き付いています。
明治・大正時代の詩人、山村暮鳥は「いちめんのなのはな」という言葉を淡々と連ねる手法で風景を表す詩をよんでいます(詩集「聖三稜玻璃」収録の詩「風景」)。
菜の花は、菜っ葉の花という意味で、アブラナ科の野菜の花の総称です(別名「油来」(あぶらな)、「花菜」(はなな)、「菜種」(なたね))。ほとんどは、黄色で十字型の花びらをつけます。
アブラナ科はフウチョウソウ目の一科。学名はBrassicaceae。4枚の花弁が十字架のように見えることから、昔は十字花科 (Cruciferae)と呼んだそうです。
学名の語源はキャベッだそうで、野生のアブラナ、栽培種のアブラナの他に、キャベツをはじめ、白菜、大根、カブ、ブロッコリー、小松菜、野沢菜、チンゲンサイ、カラシナなどもみんな菜の花の仲間です。大根の花は十字ですが白です。
雑草のぺんぺん草(ナズナ)やイヌガラシ、切り花でおなじみのストックなども同じ仲間、日本の薬味の代表であるワサビ、そして西洋料理に欠かせない辛み野菜、クレソンも菜の花の仲間なんです。
菜の花類は細胞に傷がつくと、細胞内の酵素が働いて辛み成分ができるのが特徴。これは、昆虫や草食動物に食べられないための重要な機能なのだそうです。
若い芽や、開きかけの花のおひたしのぴりっとしたほろ苦い甘さは、春の味覚の代表。冬の間、速度を落としていた体を目覚めさせて、夏の体への変化を促してくれます。

無尽蔵に収穫できる食と、灯りの資源だった菜種
花はやがて、つんと尖ったたくさんのさやになり、さやの中に直径1ミリほどの小さな種をびっしり実らせます。これが来種です。
昔は、菜種は粒のまま薬味や和え衣などにしても食べたそうです。香川のうどんの昔の食べ方に、野生のカラシの種をすって、薬味にして食べたという記録があります。マスタードやカラシは、カラシナの種から油分を分離して残った粉です。粒のままのマスタードもありますね。
とはいえ、ゴマなどのように食料としてどんどん食べるというものではないので、そのままでは、種としては多すぎます。
無尽蔵に収穫できてしまうこの菜種、食料としては需要がごく少ないのですが、煎って絞ると、おいしい黄金色の香ばしい油がとれるのです。菜種の種子の含油量は40%、比重は0.9です。菜種油は、古くから食用、灯火用、潤滑油として使われてきました。
そして、近年では、自動車を動かす軽油としても使えることがわかり、ドイツ、そして日本各地で、石油に代わる循環型エネルギーとしての研究が進んでいます。
すばらしいでしょう! その上、搾った粕は一部のカラシ用以外は食用には向きませんが、とても良い肥料になるのです。成分は窒素約5%、五酸化リン約2.5%。「油粕」といえば「菜種油粕」を指すほど、菜種の絞り粕はよい肥料として畑で活躍してきました。
菜種油を食べることは、生態系の循環と体の健康の双方にとって負荷が少ないだけでなく、環境保全や栄養的価値もとても高いのです。
昔の日本では、油といえば、菜種かゴマを搾ったものだったということです。
近代技術で精製した菜種油は色も匂いもなく「白絞油(しらしめゆ)」または「水晶油」と呼ばれますが、近年は精製した大豆油や綿実油も白絞油と呼ばれるので注意が必要です。市販の天ぷら油などに使われているのは菜種油といってもこの白絞油の方です。
後編につづく